|

<2025年6月、ハイブリッド型半期方針共有会を開催>
2025年6月13日、株式会社ゼロインは本社オフィスにて半期方針共有会を開催しました。コロナ禍以降オンライン配信のみで実施してきた本イベントですが、社員からの要望を受け、今回初めて「ライブ参加」と「オンライン参加」を選択できるハイブリッド形式で実施。社員一人ひとりの働き方に合わせた参加スタイルを提供することで、参加率と満足度の向上に成功しました。
<ハイブリッド型社内イベントの効果と成功要因>
社員の声から生まれた新しい開催形式
当社では半期方針共有会をコロナ禍以降、オンライン配信のみで実施してきました。しかし、「対面でのコミュニケーションを取りたい」「経営陣の話をライブで聞きたい」という社員の声が増えてきたことから、今回ハイブリッド形式での開催に踏み切りました。
この決断により、以下のような効果が得られました:
各自の状況や希望に合わせた参加形態を選択可能に
オフィス参加者同士の直接的なコミュニケーション機会の創出
遠方や時間的制約のある社員も平等に参加できる環境の維持
<部門横断コミュニケーションの活性化>
イベント後に開催した懇親会では、普段接点の少ない部門間の社員同士が交流する姿が多く見られました。参加者からは「異なる部署の方と話せて新しい視点が得られた」「部門を超えたコラボレーションのきっかけになった」といった前向きな感想が多数寄せられています。
<経営者視点:社内イベント成功の本質とは>
リクルート時代から学んだ「参加したくなる」イベント設計
私がリクルート総務部で社内イベントを担当していた際、創業者であり当時の社長だった江副浩正氏から重要な教えを受けました。
「土曜日に開催する運動会に、総務の企画力でみんなが参加したいと思うコンテンツを用意し、参加率を高めることが重要ミッション。リクルートはトップダウンの会社ではなく、ボトムアップ型の会社だから」
この言葉は、社内イベントの本質を表しています。強制ではなく「参加したい」と思わせる魅力的なコンテンツ設計こそが、真の成功につながるのです。

<現代の経営者として心がけていること>
経営者となった今、私が常に意識しているのは「ライブで話を聞いてみたいと思わせる経営メッセージ」の発信です。形式的な情報共有ではなく、社員の心に響き、行動変容を促すメッセージをどう届けるか。江副氏から学んだ「参加したくなる」という原則は、今日のハイブリッド型イベントにおいても変わらない重要な指針となっています。
<これからの社内イベント設計のポイント>
今回の半期方針共有会の成功を踏まえ、これからの社内イベント設計において重要なポイントをまとめました:
選択肢の提供: 一律の参加形態ではなく、社員が自分に合った参加方法を選べること
双方向性の確保: オンライン参加者も含めた質疑応答や意見交換の場の設定
部門横断交流: 普段接点のない社員同士が交流できる仕掛けづくり
魅力的なコンテンツ: 「参加したい」と思わせる内容の企画
フォローアップ: イベント後のフィードバック収集と次回への改善
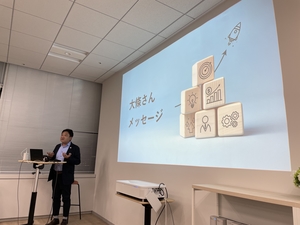
<まとめ:社員が選択できる環境づくりが鍵>
「オンライン参加がいい人はオンライン、オフィス参加がいい人はオフィス参加」という選択肢を提供することで、社員一人ひとりの状況や希望に寄り添った社内イベントが実現できます。強制ではなく「参加したい」と思わせる魅力的なコンテンツと、選択できる参加形態の提供。これこそが、これからの社内イベントのあるべき姿ではないでしょうか。
当社では今後も社員の声に耳を傾けながら、より効果的な社内コミュニケーション施策を展開していきます。
熱いぜ!
|